「宣伝したいけれど、どこまで書いていいのか分からない…」と悩む接骨院の先生へ。以下は厚生労働省が公開する最新の広告ガイドライン資料(令和7年2月18日)をもとに、広告規制の範囲とOK/NGラインをわかりやすくまとめたものです。
広告で書けること ― 法的に認められている範囲
法律や告示によって広告が認められているのは、ごく限られた項目のみ。以下はその代表例です:
- 国家資格者であること(柔道整復師など)
- 所在地・電話・営業時間などの基本情報
- 予約制・休日・夜間・出張施術(往療)の有無
- 医療保険療養費の申請ができる旨(医師同意が必要な場合はその旨を明示)
- 駐車場の有無・台数など
出典:厚労省あはき・柔整広告ガイドライン(広告可能な事項一覧) :contentReference[oaicite:1]{index=1}
広告してはいけない内容(NG例)
- 技能や施術法のアピール(例:「高技術」「○○流接骨術」など)
- 経歴宣伝(例:「有名人トレーナー」「○○大学卒」など)
- 誇大・虚偽表現(例:「必ず治る」「絶対安全」など)
- 医療機関と誤認されかねない名称(例:「クリニック」「治療所」)
- ターゲットを制限する表現(例:「女性専用」「アスリート専門」)
- 効果を印象づける表現(例:「小顔矯正」「姿勢改善」など)
出典:厚労省ガイドライン(禁止事項の具体例) :contentReference[oaicite:2]{index=2}
「広告かどうか」の判断基準(大事な基準)
以下の3要件すべてが揃うと「広告」と判断され、規制の対象になります。実質的に満たしていれば、表現を少し変えても広告と判断されます:
- 来院を誘引する目的(誘引性)
- 院名や施術者が特定できる(特定性)
- 一般人に認知される状態にある(認知性)
出典:厚労省ガイドライン(広告性判定の基準) :contentReference[oaicite:3]{index=3}
公式ウェブサイトは広告?― 基本は非広告だが注意も必要
公式サイトそのものは広告とは見なされないことが基本です。ただし、次のようなケースでは広告と判断されることがあります:
- 有料検索枠に表示されている
- SNS広告やリスティング広告として配信されている
- 第三者の口コミサイトやランキングサイトに掲載されている
出典:厚労省ガイドライン(ウェブサイトの広告扱いに関する記載) :contentReference[oaicite:4]{index=4}
記事内容まとめ
- 広告で使える情報は法律で限定されている。
- 技能・効果・誇大表現はNG。
- 「広告かどうか」は3つの要件で判断。
- 公式サイトだからと言って完全に自由ではない。
誤表現や禁止文言には十分注意し、「正直で分かりやすい集客」を心がけましょう。


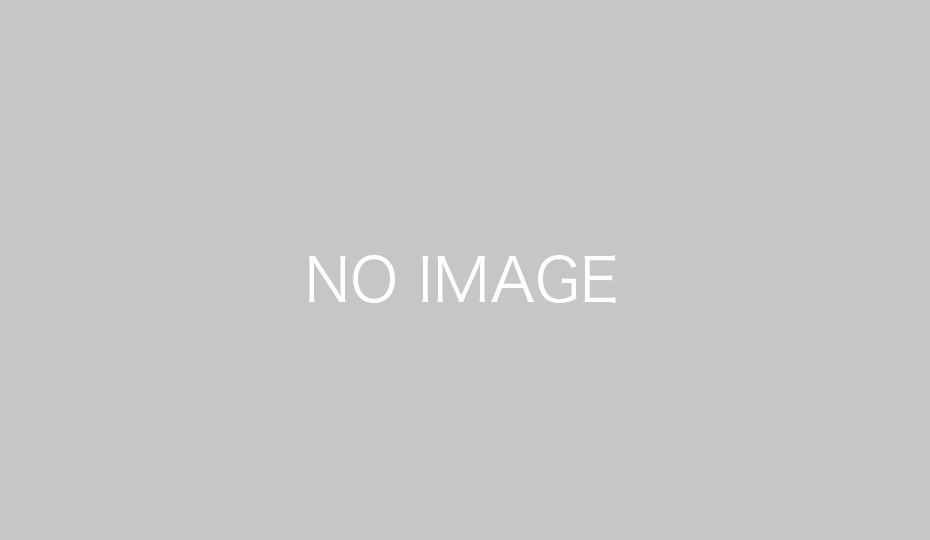
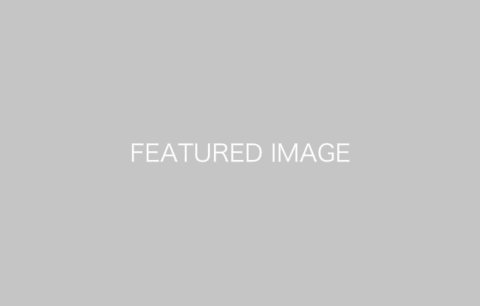

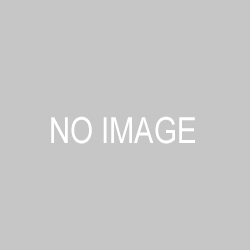
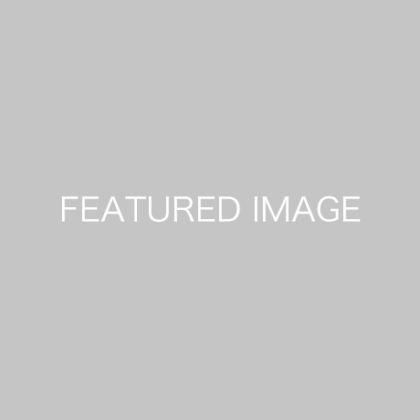

コメント